図書室開設
いらっしゃいませ、そして、あけましておめでとうございます。
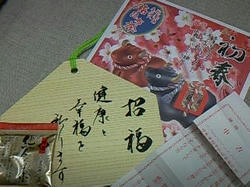
前回のブログにも書いたのですが、以前のAzulの図書室日記と、Azulブログにちょこちょこ書いていた、本の感想や情報を、専用ブログにまとめました。まだ、整理中ですが、とり急ぎ過去のものが整理できたら、新しく追加も始めていきます。
こちらからどうぞ。
前回のブログにも書いたのですが、以前のAzulの図書室日記と、Azulブログにちょこちょこ書いていた、本の感想や情報を、専用ブログにまとめました。まだ、整理中ですが、とり急ぎ過去のものが整理できたら、新しく追加も始めていきます。
こちらからどうぞ。
PR
快楽と冒険
いらっしゃいませ、

「引越し先には近所に図書館がある」と以前書いたのだけれど、本の数がそれほど多くないので、読みたいと思っている本がなかったり、出会いを求めて本棚の間をくるくる廻るのだけれど、さほどの収穫がない。3冊ほど借りて、それもぐいぐい読んだので2週間で返すことができたけれど、この2週間のタイムリミットというのがけっこうプレッシャーになる。
「第四の手」 ジョン・アーヴィング
「街道をゆく 阿波紀行・紀ノ川流域」 司馬遼太郎
「オリンピア ナチスの森で」 沢木耕太郎
「街道をゆく」では、紀州「雑賀寺」の部分でふと顔を上げた。
「あれ? 行ったことあるやんね、ここ」
去年、確か気の知れた人たちとバンに乗り込んで、和歌山ドライブツアーをした。うら寂しい境内と(確か工事中)、何かいてそうな墓地しか覚えてない。ああ、無知のままこういうところに行ってはやっぱりだめだな。とはいえ、雑賀寺に行くなんて全然頭になかったし、かといって行くと分かっていてピンポイントで司馬さんのこの本を選ぶのは不可能に近い。こういうときは、もう一度行くしかないのだ。
「オリンピア ナチスの森で」では、レニ・リーフェンシュタールのことと、彼女の「民族の祭典」のことを知る。
「え? レニ・リーフェンシュタールって、『ヌバ』の人!!?」
「へえー、『民族の祭典』って、単なる”ナチス万歳"オリンピックの話じゃないのか」
2冊読んだあたりで、自分の無知さを思い知るが、どんな瞬間も「新しいことを知るチャンス」を提供してくれる、この「読書」という、「人間にだけ許された『快楽』」にまたもやガツンとやられる。
なので、「本を読む習慣のない人」「一時期、本を読み漁った時期を経ていない人」っていうのは、共感できない人が多い。私の世代は、子供の頃から普通に本を馴染んできている人が多いけれど、ある年齢層の人たちにはけっこうこういう人がいる。もちろん、今は映像やネットなんかで、いろんな知識欲は満たせるかもしれないけれど、その深みや、冒険にも似たときめきは本にはかなわないなぁ、って思う。
さて、図書館の本を読み終えた後は、
「読みかけで積んどかれてる本を、ちゃんと読み終わる」
という課題を自分に与えてみた。
「自伝の小説」 李昂
「ピギー・スニードを救う話」 ジョン・アーヴィング
「自伝の小説」は、まあ読むのはきつい。いろんな理由があるので、ここでは述べないが、まあ内容そのものも重い。なので、仕事から帰って、夜寝床で読むにはあまりにしんどく、放置されていたのだ。今回もきつかったけど頑張った。全く知らなかった「謝紅雪」という人の存在を知る。この本を読んだ後、台湾の歴史や中国との関係を、今までは「点」で捉えていたことに初めて気づいた。この本は1人の女性を通して、「線」としてそれらを再考できる。それによって、私自身の意見や気持ちが変わることはないのだが、新しい視点を得たことで、その意見や気持ちの「層」が厚くなったように感じた。これも、醍醐味。
「ピギー・スニードを救う話」はどうしてほったらかしになってたんだろ。短編集だから、いつでも読めると思ってほっておかれたのかなぁ。いやあ、アーヴィングは短編も面白い。淡々と風景や心象が流れて、何事も起きずに「思わせぶり風船」がフワフワ舞うような短編も多いけれど、ちゃんと短い中に色々な事件を混ぜ込むこの筆力はさすが。だってこの人、長編の中で登場人物が書いた「短編」を入れ込んじゃう人だもの。「ペンション・グリルパルツァー」は、「ガープの世界」の中でガープが書いた処女作。その後の「ホテル・ニューハンプシャー」のエッセンスも楽しめる一品。この短編のフルコースは美味しかったです。
そんなこんなを書いていたら、また本を探しに行きたくなった。図書館、本屋、そして自分の本棚。人に「面白い本ない?」って聞くのも楽しい。自分探しより絶対ためになる、本探しの旅。
「引越し先には近所に図書館がある」と以前書いたのだけれど、本の数がそれほど多くないので、読みたいと思っている本がなかったり、出会いを求めて本棚の間をくるくる廻るのだけれど、さほどの収穫がない。3冊ほど借りて、それもぐいぐい読んだので2週間で返すことができたけれど、この2週間のタイムリミットというのがけっこうプレッシャーになる。
「第四の手」 ジョン・アーヴィング
「街道をゆく 阿波紀行・紀ノ川流域」 司馬遼太郎
「オリンピア ナチスの森で」 沢木耕太郎
「街道をゆく」では、紀州「雑賀寺」の部分でふと顔を上げた。
「あれ? 行ったことあるやんね、ここ」
去年、確か気の知れた人たちとバンに乗り込んで、和歌山ドライブツアーをした。うら寂しい境内と(確か工事中)、何かいてそうな墓地しか覚えてない。ああ、無知のままこういうところに行ってはやっぱりだめだな。とはいえ、雑賀寺に行くなんて全然頭になかったし、かといって行くと分かっていてピンポイントで司馬さんのこの本を選ぶのは不可能に近い。こういうときは、もう一度行くしかないのだ。
「オリンピア ナチスの森で」では、レニ・リーフェンシュタールのことと、彼女の「民族の祭典」のことを知る。
「え? レニ・リーフェンシュタールって、『ヌバ』の人!!?」
「へえー、『民族の祭典』って、単なる”ナチス万歳"オリンピックの話じゃないのか」
2冊読んだあたりで、自分の無知さを思い知るが、どんな瞬間も「新しいことを知るチャンス」を提供してくれる、この「読書」という、「人間にだけ許された『快楽』」にまたもやガツンとやられる。
なので、「本を読む習慣のない人」「一時期、本を読み漁った時期を経ていない人」っていうのは、共感できない人が多い。私の世代は、子供の頃から普通に本を馴染んできている人が多いけれど、ある年齢層の人たちにはけっこうこういう人がいる。もちろん、今は映像やネットなんかで、いろんな知識欲は満たせるかもしれないけれど、その深みや、冒険にも似たときめきは本にはかなわないなぁ、って思う。
さて、図書館の本を読み終えた後は、
「読みかけで積んどかれてる本を、ちゃんと読み終わる」
という課題を自分に与えてみた。
「自伝の小説」 李昂
「ピギー・スニードを救う話」 ジョン・アーヴィング
「自伝の小説」は、まあ読むのはきつい。いろんな理由があるので、ここでは述べないが、まあ内容そのものも重い。なので、仕事から帰って、夜寝床で読むにはあまりにしんどく、放置されていたのだ。今回もきつかったけど頑張った。全く知らなかった「謝紅雪」という人の存在を知る。この本を読んだ後、台湾の歴史や中国との関係を、今までは「点」で捉えていたことに初めて気づいた。この本は1人の女性を通して、「線」としてそれらを再考できる。それによって、私自身の意見や気持ちが変わることはないのだが、新しい視点を得たことで、その意見や気持ちの「層」が厚くなったように感じた。これも、醍醐味。
「ピギー・スニードを救う話」はどうしてほったらかしになってたんだろ。短編集だから、いつでも読めると思ってほっておかれたのかなぁ。いやあ、アーヴィングは短編も面白い。淡々と風景や心象が流れて、何事も起きずに「思わせぶり風船」がフワフワ舞うような短編も多いけれど、ちゃんと短い中に色々な事件を混ぜ込むこの筆力はさすが。だってこの人、長編の中で登場人物が書いた「短編」を入れ込んじゃう人だもの。「ペンション・グリルパルツァー」は、「ガープの世界」の中でガープが書いた処女作。その後の「ホテル・ニューハンプシャー」のエッセンスも楽しめる一品。この短編のフルコースは美味しかったです。
そんなこんなを書いていたら、また本を探しに行きたくなった。図書館、本屋、そして自分の本棚。人に「面白い本ない?」って聞くのも楽しい。自分探しより絶対ためになる、本探しの旅。
「安安の夏休み」を過ごす
いらっしゃいませ、
「安安の夏休み」は、映画「冬冬(とんとん)の夏休み」の原作。なぜ「安安」が「冬冬」になったか?っていうのは分からない。
「冬冬(とんとん)の夏休み」は、台湾の巨匠、ホウ・シャオシェン監督の80年代の作品である。この原作を書いた朱天文さんは台湾で人気の女流作家だそうで、私も他に「台北ストーリー」「荒人日記」を読んだことがある。昔から、ホウ・シャオシェン監督と一緒に脚本を書いたりしていたそうなので、映画はこの原作の細部まで、いやそれ以上に丁寧に作られていて、原作がノベライズではないかと思うくらい。
お話はとてもシンプルで、母親が出産間近なため、夏休みに田舎の祖父母の家に預けられる幼い兄妹の小さな成長物語、といった風情。
その中で、懐かしさを特に覚えるのが、祖父母と孫達の関係。大人たちは幼い子供たちが来たからといって、特に生活習慣を変えたりはしない。大人が決めたルールを子供たちがやぶると叱るし、子供たちもやっぱりやりたいことはやりたいわけだから、大人の目を盗んでいろいろ悪さをする。けれど、祖父母(特に祖父)に対して、子供たちは敬意を持っている。「認めて欲しい」という切ない気持ちも持っている。そしてまた、子供たちの純粋な思いや好意に、大人たちの色のつきすぎた心が少し溶け出したりする。
そんな関係が懐かしい。私が幼い頃、祖父母は私たち孫を「猫可愛がり」はしなかった。孫の言いなりには、絶対にならなかった。悲しいぐらい・・・。そういえば、父が孫を叱り飛ばしているところをみたことがない。できないのだろうな。だから親以外の親族で怒鳴っているのは私だけ。ほほ。
そんな懐かしい思いと、日本の旧き農村に似た風景を感じながら読むと、さらにじわじわくる物語である。それをそのまま映像で味わうことができるのが「冬冬の夏休み」(映画)。
TSUTAYAのアジアコーナーに出かけていって、その95%が「韓流」と「台湾コミックドラマ」である事実に、ガラガラとその思いは崩れ去り、とぼとぼと家路へ向かうのでありました。セルビデオではあるようです。秋の夜長にはちょうどここちよいかもしれないな。
「安安の夏休み」は、映画「冬冬(とんとん)の夏休み」の原作。なぜ「安安」が「冬冬」になったか?っていうのは分からない。
「冬冬(とんとん)の夏休み」は、台湾の巨匠、ホウ・シャオシェン監督の80年代の作品である。この原作を書いた朱天文さんは台湾で人気の女流作家だそうで、私も他に「台北ストーリー」「荒人日記」を読んだことがある。昔から、ホウ・シャオシェン監督と一緒に脚本を書いたりしていたそうなので、映画はこの原作の細部まで、いやそれ以上に丁寧に作られていて、原作がノベライズではないかと思うくらい。
お話はとてもシンプルで、母親が出産間近なため、夏休みに田舎の祖父母の家に預けられる幼い兄妹の小さな成長物語、といった風情。
その中で、懐かしさを特に覚えるのが、祖父母と孫達の関係。大人たちは幼い子供たちが来たからといって、特に生活習慣を変えたりはしない。大人が決めたルールを子供たちがやぶると叱るし、子供たちもやっぱりやりたいことはやりたいわけだから、大人の目を盗んでいろいろ悪さをする。けれど、祖父母(特に祖父)に対して、子供たちは敬意を持っている。「認めて欲しい」という切ない気持ちも持っている。そしてまた、子供たちの純粋な思いや好意に、大人たちの色のつきすぎた心が少し溶け出したりする。
そんな関係が懐かしい。私が幼い頃、祖父母は私たち孫を「猫可愛がり」はしなかった。孫の言いなりには、絶対にならなかった。悲しいぐらい・・・。そういえば、父が孫を叱り飛ばしているところをみたことがない。できないのだろうな。だから親以外の親族で怒鳴っているのは私だけ。ほほ。
そんな懐かしい思いと、日本の旧き農村に似た風景を感じながら読むと、さらにじわじわくる物語である。それをそのまま映像で味わうことができるのが「冬冬の夏休み」(映画)。
TSUTAYAのアジアコーナーに出かけていって、その95%が「韓流」と「台湾コミックドラマ」である事実に、ガラガラとその思いは崩れ去り、とぼとぼと家路へ向かうのでありました。セルビデオではあるようです。秋の夜長にはちょうどここちよいかもしれないな。
女ひとりじゃないけれど47都道府県行ってみたい
いらっしゃいませ、
ちょっと軽いものを読みたいなぁ、と思って、
「47都道府県女ひとりで行ってみよう」(益田ミリ著)
益田ミリといえば、このブログでも書いたことのある「結婚しなくていいんですか」の著者だから、もしかして重くなるかも、って思ったんだけど、私もひとり旅を何度かしているので、共感できる部分と、んー、ちょっとめんどくさいなぁ、この人、って思う部分と、もっとモノを知っといた方がいいよ、とかがあったりで、やっぱり単に軽い本ではなかったです。でも、この人、1人以外の旅のときは、それなりに協調できる人かもしれない、とふと思いました。旅に出る前よりずっといろんなことを今は知っていると思う。(ところが、この人はそれを「可愛げがなくなった」としてしまう。この辺もちょっと理解できない私。) まあ、一人旅ができる人は、できない人より(できないというか、しようとしない人より)よき連れとなるものです。
さて、47都道府県に生きているうちに行けるか?だーいぶ前にどの県に行っていないかどこかに書いた記憶があるのだけれど、あの時から行っていない県はひとつしか減らなかった。
「徳島県」

あ、これは、徳島市の「リスボン・モラエス広場」のジャカランダです。
今はここ数年で一番多く行く県となりました。縁というのは不可思議なものです。
なので残りは...
山形県
群馬県
山口県
大分県
長崎県
宮崎県
熊本県
となった。
やっぱり九州は遠い。北海道は「函館」とか「札幌」とか行けば征服したことになるけど、九州はなぁ、ようけあるもんなぁ。
益田さんの本によると、山形県の女の人はとても感じがいいらしい。青森で聞いた評とはだいぶ違う。やっぱり実際に旅をしてみるべきなのかも。
ちょっと軽いものを読みたいなぁ、と思って、
「47都道府県女ひとりで行ってみよう」(益田ミリ著)
益田ミリといえば、このブログでも書いたことのある「結婚しなくていいんですか」の著者だから、もしかして重くなるかも、って思ったんだけど、私もひとり旅を何度かしているので、共感できる部分と、んー、ちょっとめんどくさいなぁ、この人、って思う部分と、もっとモノを知っといた方がいいよ、とかがあったりで、やっぱり単に軽い本ではなかったです。でも、この人、1人以外の旅のときは、それなりに協調できる人かもしれない、とふと思いました。旅に出る前よりずっといろんなことを今は知っていると思う。(ところが、この人はそれを「可愛げがなくなった」としてしまう。この辺もちょっと理解できない私。) まあ、一人旅ができる人は、できない人より(できないというか、しようとしない人より)よき連れとなるものです。
さて、47都道府県に生きているうちに行けるか?だーいぶ前にどの県に行っていないかどこかに書いた記憶があるのだけれど、あの時から行っていない県はひとつしか減らなかった。
「徳島県」
あ、これは、徳島市の「リスボン・モラエス広場」のジャカランダです。
今はここ数年で一番多く行く県となりました。縁というのは不可思議なものです。
なので残りは...
山形県
群馬県
山口県
大分県
長崎県
宮崎県
熊本県
となった。
やっぱり九州は遠い。北海道は「函館」とか「札幌」とか行けば征服したことになるけど、九州はなぁ、ようけあるもんなぁ。
益田さんの本によると、山形県の女の人はとても感じがいいらしい。青森で聞いた評とはだいぶ違う。やっぱり実際に旅をしてみるべきなのかも。
ミントジュレップな初夏
いらっしゃいませ、
更新をかなりサボっていたですね。もう6月も半ばです。何をしていたのだろう。。。
「空海の風景」を読み終わりました。長い旅を終えたような寂寥感がありました。
でもやっぱり、「密教」って何をやるもんなのか分からない。だから「密」なの?
「街道を行く オランダ紀行」を読み終わりました。いやあ、オランダ面白かったです。
旅に疲れて、クラシックな米文学に戻ってみました。サリンジャーとカポーティ。サリンジャーは「ナイン・ストーリーズ」を。Kの世代は、アニメにこの伝説の短編集へのオマージュが盛り込まれていたらしく、知識として知っている。じゃあ、ほんものを、と野崎 孝さん訳のものを買ってきました。私が以前読んだのは別の人の訳の「九つの物語」だった。「バナナフィッシュに最適の日」「バナナ魚日和」「バナナフィッシュにうってつけの日」、どのタイトルがベストでしょう。
カポーティは「ティファニーで朝食を」。オードリー・ヘップバーンでたいそう有名な映画の原作ですが、全然映画と違うそうです。もともとオードリー・ヘップバーンの映画をあまり好きはない私が、本の表紙がその映画である文庫本に手が伸びなかったのですが、村上春樹氏の訳で最近出たものを買ってみました。
いやぁ、原作のホリーの役はオードリーじゃ無理でした。だから映画は全然違ってたのでしょうか。映画もちゃんと観てみようと思いました。
Wowowでずーっと全仏オープンを見ていたので、総理大臣の顔とか大統領の顔を忘れそうです。
Wowowで何気なく「ラブソングができるまで」を観ていたら、最後まで観てしまいました。
ヒュー・グランドのPVが最高です。
岡田君の映画のDVDが中古であったので衝動買いをしてしまいました。団地妻の昼下がりの浮気です。
Wiiをかなりサボっています。
これからすることは...
7月のはじめに1週間ぐらいポルトガルに行きます。頭を悩ませているのは、帰りのスキポール空港(アムステルダム)での待ち時間なのですが、面白そうなのを見つけました。
http://www.hollandtoursschiphol.nl/
待ち時間が長い人のための、スキポール発プチツアー。他の空港にもあるのかしら?
8月の徳島ジャズストリートに、「出演」します。ただいま練習中。相変わらず「猛練習」をしない私ですが。
一歩でも半歩でも、少しずつ。後ろに下がっても全然かまわずに。
更新をかなりサボっていたですね。もう6月も半ばです。何をしていたのだろう。。。
「空海の風景」を読み終わりました。長い旅を終えたような寂寥感がありました。
でもやっぱり、「密教」って何をやるもんなのか分からない。だから「密」なの?
「街道を行く オランダ紀行」を読み終わりました。いやあ、オランダ面白かったです。
旅に疲れて、クラシックな米文学に戻ってみました。サリンジャーとカポーティ。サリンジャーは「ナイン・ストーリーズ」を。Kの世代は、アニメにこの伝説の短編集へのオマージュが盛り込まれていたらしく、知識として知っている。じゃあ、ほんものを、と野崎 孝さん訳のものを買ってきました。私が以前読んだのは別の人の訳の「九つの物語」だった。「バナナフィッシュに最適の日」「バナナ魚日和」「バナナフィッシュにうってつけの日」、どのタイトルがベストでしょう。
カポーティは「ティファニーで朝食を」。オードリー・ヘップバーンでたいそう有名な映画の原作ですが、全然映画と違うそうです。もともとオードリー・ヘップバーンの映画をあまり好きはない私が、本の表紙がその映画である文庫本に手が伸びなかったのですが、村上春樹氏の訳で最近出たものを買ってみました。
いやぁ、原作のホリーの役はオードリーじゃ無理でした。だから映画は全然違ってたのでしょうか。映画もちゃんと観てみようと思いました。
Wowowでずーっと全仏オープンを見ていたので、総理大臣の顔とか大統領の顔を忘れそうです。
Wowowで何気なく「ラブソングができるまで」を観ていたら、最後まで観てしまいました。
ヒュー・グランドのPVが最高です。
岡田君の映画のDVDが中古であったので衝動買いをしてしまいました。団地妻の昼下がりの浮気です。
Wiiをかなりサボっています。
これからすることは...
7月のはじめに1週間ぐらいポルトガルに行きます。頭を悩ませているのは、帰りのスキポール空港(アムステルダム)での待ち時間なのですが、面白そうなのを見つけました。
http://www.hollandtoursschiphol.nl/
待ち時間が長い人のための、スキポール発プチツアー。他の空港にもあるのかしら?
8月の徳島ジャズストリートに、「出演」します。ただいま練習中。相変わらず「猛練習」をしない私ですが。
一歩でも半歩でも、少しずつ。後ろに下がっても全然かまわずに。
寝床に積まれていると、ホッとするっていうか
「え?!、jさんってお料理できるんですか?」
って言われた。できるよ。
さて、ちょっとイライラしていたときに本屋さんに行って、あまり考えなくて読める本を、って思って選んだ本が2冊。
益田ミリ作 「結婚しなくていいですか?」考えなくて、って思ったのに、「結婚しなくていいですか?」は、いろいろ考えてしまいます。
有川 浩作 「阪急電車」
「なんで、junちゃんがこのタイトルの本買うの?」ってKに訊かれたけど、こう言われ続けたり、いいのかなぁって考えたりした期間が長かった私にとって、とてもすーっと入ってきたり、ごつごつ入ってきたりするものがありました。仕事のこと、家族のこと、出会いのこと、出産のこと、老後のこと、介護のこと...想像力のない老若男女から受け続けるセクハラ。未だに「子供は?」って訊く人いますし。「老後寂しいよ」とか、意味不明のこともいいます、こういう人って。子供がいたって寂しい人は寂しいのに。なので、主人公のふーちゃんやさわこさんの気持ちがとても普通に自然にわかります。人に「結婚っていいよ」「子供産まないの?」「親と住んでるの?パラサイト?」とかを何気なく言ったことのある人、ぜひこの本読んで、頭よくなってください。
「阪急電車」のほうは...これは本当になんも考えずに読めます。発想は面白いのですが、文章力があまりないので、文学とゆうよりドラマの脚本かな。でも、今津線って。そんな舞台を選んだところは面白い。ご存知ないかたはぜひ一度乗ってみてくださいな。あと、夙川線とか。箕面線とか。阪急電車好きの甥っ子に読んだあとあげようかな、って思ったけど、同僚に婚約者取られた女の話とか、ちょっと子供にはなぁ。
そろそろ「空海の風景」にも戻らないと。(これがなかなか読み進まない。八十八ヶ所巡り並み!)
本探しは、自分探しより楽しい。多分。
ぐいぐい読み進むわけではないけれど
いらっしゃいませ、
今、読んでいる本は「その名にちなんで」(The Namesake)。映画にもなって、最近公開されたそうなのだけれど、どこでやってたかはわからない。大阪はまだかもしれない。終ったのかもしれない。
インド人の夫婦が、仕事で身を立てるためにアメリカに住み、アメリカで子供を育て、そしてその子供がインド人としての、アメリカ人としての、アイデンティティに悩みながら成長し、いつか両親の生き方を理解していく、といった、悪く言うとよくあるっぽい話なのだが、小説はプロットの面白さが命だとは私はまったく思っていないので、こういうどこにでもある題材を優れた文章力で表現している本に出会うと、とても嬉しいのだ。
ストーリーが奇想天外なわけではないので、映画化はどうか、って話になるのだけれど、こういう話のほうが逆に映像の美しさや音楽の美しさ、俳優の巧さなどが素直に入ってきて、映画館なんかで観るととてもいい気分になると思うのだ。
今、読んでいる本は「その名にちなんで」(The Namesake)。映画にもなって、最近公開されたそうなのだけれど、どこでやってたかはわからない。大阪はまだかもしれない。終ったのかもしれない。
インド人の夫婦が、仕事で身を立てるためにアメリカに住み、アメリカで子供を育て、そしてその子供がインド人としての、アメリカ人としての、アイデンティティに悩みながら成長し、いつか両親の生き方を理解していく、といった、悪く言うとよくあるっぽい話なのだが、小説はプロットの面白さが命だとは私はまったく思っていないので、こういうどこにでもある題材を優れた文章力で表現している本に出会うと、とても嬉しいのだ。
ストーリーが奇想天外なわけではないので、映画化はどうか、って話になるのだけれど、こういう話のほうが逆に映像の美しさや音楽の美しさ、俳優の巧さなどが素直に入ってきて、映画館なんかで観るととてもいい気分になると思うのだ。
サンマのお造りというしあわせ
昨日の土曜日はお仕事。まあ先週いっぱい休んだし。仕事帰りに、カバン探しで梅田を俳諧していたKと、友人のYちゃんと合流して、晩御飯。
メニューに何気なく、ポルトガル料理。やはり大阪は楽しいですねぇ。ちなみに居酒屋価格で一皿450円。やはり大阪は、妥当ですねぇ。いただいたのは、サンマのお造りなどでしたが。
ハワイの写真が焼きあがってきて、ただしフジの100の焼き上がりの「青」が気に入らない。マクロマックスで撮った方だ。一眼レフにPLフィルタをつけて撮ったやつは、やっぱり青が濃厚だった。で、一応持っていったモノクロフィルムはやっぱり使わなかった。「虹、モノクロで撮ってみたら」、っていうKの発言がツアーバスの中で受けてたな。
「ナラ・レポート」 津島佑子
「バゴンボの嗅ぎタバコ入れ」 カート・ヴォネガット
カート・ヴォネガットさんって、今年の始めに亡くなっていたんだ。知らなんだ。20世紀の名作「スローターハウス5」、「デッドアイディック」「母なる夜」なんかが好きだった。また一人、愛すべき変人が去る。やれやれ。合掌。
KへのプレゼントにB・セッツアーのニューアルバムを買う。久々にTレコへ。レジが遅いなぁ、ここ相変わらず。たくさんレジはあるんだけど、どこも行列。ブライアン・セッツァー・オーケストラの「ウルフギャングス・ビッグ・ナイト・アウト」。ウルフギャングと言えば、このおじさんの顔つきの缶詰をハワイのスーパーでよく見かけた。有名な人だったのね。(ワイキキでレストランちゅうよりファーストフード風のカフェは見た)
2つ目の写真は、マウナ・ケア オニズカセンター付近(2800メートルぐらい)での虹。
No Music, No Problem
飛行機とビーチ用の本を3冊買った。
なんか、いい感じで選べた。
村田エフェンディ滞土禄(梨木香歩) 100年前のトルコ留学生の青春期。
忘却の河(福永武彦) 「廃市」が有名な、池澤夏樹のお父上の作品。
クォン・デ(森達也) 日本で人知れずこの世を去ったベトナム「ラストエンペラー」。
MP3は持っていかない。音楽はなくても過ごせるタチなのだ。たぶん生きていけるだろう。何かがなければ生きていけない、と考えてたら、生きていけない。何を食っても、まず生きていくのだ。
音はどうだろう。「形而上的な音」が感じられれば、多分生きていけるだろう、って思う。無音という音。お、「Sound of Silence」ぢゃないか。
そういえば、若い友人のYちゃんも、音楽がなくても生きていけるタチだ、ってブログで書いてたな。若いのに、大したものだ。(もう、縁側のおばあちゃん気分だ。)
火山の音って、どんなんだろう。。。・
「欲望の翼」のオープニングのような庭を妄想してみる。
いらっしゃいませ、
さて、我が家の草花たち。夏は日が高いので、南向きのベランダの日射範囲が小さくなる。そうなると、花々に元気がない。まずアジサイが早々と「葉アジサイ」に。つづいて「ブルーハワイ」が元気がなくなり逝去。スイートバジルも、小ぶりの葉っぱが我が家の食卓に色を添えた以降は、いっこうに大きくならず、本日撤退。で、なぜかサボテンなのに「金のなる木」が絶滅。お祝いに頂いた「多幸の樹(ガジュマル)」は頑張っているから、T家は、金はならないけど幸せはいっぱいなのさ、と自らを励ます。
「掘りごたつ屋敷」のお庭の枝豆に触発されて、我が家でも小さな鉢植えに試しに植えてみたら、あれってツル系の植物なので、伸びる、伸びる。本当は添木をしてやらないといけないのだけれど、そのまんまにしていたら、ベランダを這いつくばりながら、小さな実を付け出した。
空の鉢植えは見ていると寂しくなるので、今日は、「山本」に遠出をして、草花の補充に。
「村上春樹のなかの中国」を読み終わる。「欲望の翼」を思う。今再び、90年代のウォン・カーワイを観たら、私は何を感じるのだろうか。私の、失われた、それでも確かに存在した90年代。「阿Q正伝」も読んでみたくなる。そういえば、「欲望の翼」の原題は「阿飛正伝」だった。評論はあくまで評論だけど、コロコロといろんなものが拾えるのが面白い。
朱天文の「荒人手記」も、眠れない夜にちょうどよい。チャン・チェンやリー・カーションなんかを思い浮かべて読みふける。
でも最近すぐに目が疲れて、大量に読み漁ることができない。
ブルーベリーでも植えようかしら。
さて、我が家の草花たち。夏は日が高いので、南向きのベランダの日射範囲が小さくなる。そうなると、花々に元気がない。まずアジサイが早々と「葉アジサイ」に。つづいて「ブルーハワイ」が元気がなくなり逝去。スイートバジルも、小ぶりの葉っぱが我が家の食卓に色を添えた以降は、いっこうに大きくならず、本日撤退。で、なぜかサボテンなのに「金のなる木」が絶滅。お祝いに頂いた「多幸の樹(ガジュマル)」は頑張っているから、T家は、金はならないけど幸せはいっぱいなのさ、と自らを励ます。
「掘りごたつ屋敷」のお庭の枝豆に触発されて、我が家でも小さな鉢植えに試しに植えてみたら、あれってツル系の植物なので、伸びる、伸びる。本当は添木をしてやらないといけないのだけれど、そのまんまにしていたら、ベランダを這いつくばりながら、小さな実を付け出した。
空の鉢植えは見ていると寂しくなるので、今日は、「山本」に遠出をして、草花の補充に。
「村上春樹のなかの中国」を読み終わる。「欲望の翼」を思う。今再び、90年代のウォン・カーワイを観たら、私は何を感じるのだろうか。私の、失われた、それでも確かに存在した90年代。「阿Q正伝」も読んでみたくなる。そういえば、「欲望の翼」の原題は「阿飛正伝」だった。評論はあくまで評論だけど、コロコロといろんなものが拾えるのが面白い。
朱天文の「荒人手記」も、眠れない夜にちょうどよい。チャン・チェンやリー・カーションなんかを思い浮かべて読みふける。
でも最近すぐに目が疲れて、大量に読み漁ることができない。
ブルーベリーでも植えようかしら。
プロフィール
HN:
DonaT
HP:
性別:
女性
自己紹介:
被写体に恋をしたらシャッターを押し、フワフワしてきたら文章を書き、もわもわしてきたら花に水をやっています。
写真のこと、旅のこと、本のこと、言葉のこと、音のこと、などを描いて撮ってます。
写真のこと、旅のこと、本のこと、言葉のこと、音のこと、などを描いて撮ってます。
ついったー
最新記事
(12/10)
(07/14)
(05/15)
(05/03)
(04/22)
(03/20)
(03/11)
(03/04)
(02/13)
(01/15)
(12/26)
(11/20)
(11/03)
(10/31)
(10/28)
(10/21)
(10/11)
(10/08)
(10/02)
(09/23)
(09/21)
(09/18)
(09/14)
(09/12)
(09/10)
カテゴリー
最新コメント
アーカイブ
最古記事
(10/31)
(11/02)
(11/03)
(11/06)
(11/07)
(11/12)
(11/19)
(11/22)
(11/25)
(11/29)
(12/08)
(12/14)
(12/19)
(12/28)
(12/31)
(12/31)
(01/06)
(01/07)
(01/17)
(01/25)
(01/29)
(02/05)
(02/13)
(02/17)
(02/23)

